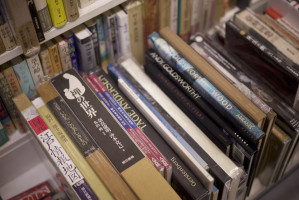booost technologies、「ABtC アプリケーション認証」を取得ウラノス・エコシステム相互接続対応し、欧州電池規則への対応を加速
リリース発行企業:booost technologies株式会社

統合型SXプラットフォーム「サステナビリティERP(※1)」の提供と「サステナビリティ2026問題」の提唱により企業のサステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)(※2)の加速を支援するbooost technologies株式会社(東京都品川区、代表取締役:青井宏憲 以下 当社)は、環境規制への対応と社会課題の解決を業界協調で行うことで産業全体の競争力の向上に貢献する「一般社団法人自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センター(以下 ABtC/Automotive and Battery Traceability Center)」によるABtCの認証プログラムにおいて、「booost Sustainability Cloud」がウラノス・エコシステムと相互接続ができるアプリケーションとして「アプリケーション認証」を取得いたしました。
これにより、当社が開発・運営を行う「booost Sustainability Cloud(グローバル85ヶ国以上192,000拠点で利用)」のユーザーは、OEM、バッテリーメーカー、原材料サプライヤーに至るまで、自動車・蓄電池サプライチェーンにかかるPCF(Product Carbon Footprint、以下PCF)に関わる機能を、より安心してサービスをご利用いただくことが可能となります。
■ 認証プログラム概要
認証プログラムとは、ABtCが提供するデータ連携基盤と安全に接続できるCFP(Carbon Footprint:以下CFP)算定アプリケーションや、ABtCのサービスを正しく理解した上でシステム運用や業務支援を行うことができる事業者を認証するためのプログラムです。この認証により、トレーサビリティサービス利用者(ユーザー)が、品質保証されたアプリケーションを利用することができ、ABtCから認証された事業者から正しく業務支援を受けることができることが可能となります。
当社は、ABtCの認証プログラムのうち、CFP算定アプリケーションを対象とする「アプリケーション認証」を取得いたしました。当社は、製品のライフサイクル全体を通して排出されるCO2排出量(PCF)をより精緻に算出する「booost PCF」機能を提供しており、自動車・蓄電池の関連製品においても、精緻な算定やボトルネックを可視化、PCF改善のための高度な分析を行います。
<認証概要>
団体: 一般社団法人 自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センター(ABtC)
認証の種類: 認証プログラム 「A」アプリケーション認証(対象:CFP算定アプリケーション)
認証内容: 提供するCFP算定アプリケーションが、ガイドラインに従って基盤上で安全かつ安定して相互接続できること。ABtCのデータ連携基盤にアプリケーションを接続するためには、本認証を取得する必要があります。
認証期間: 2025年4月7日 ~ 2027年4月6日
<一般社団法人 自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センター(ABtC)について>
ABtCは、自動車及び蓄電池のサプライチェーン全体で、安全かつ安心なデータ共有を実現するために設立された一般社団法人です。2024年2月に設立され、同年5月からは蓄電池のカーボンフットプリント(CFP)データをサプライチェーン全体で連携・集計する「トレーサビリティサービス」の提供を開始しました。さらに、9月には日本初の「公益デジタルプラットフォーム運営事業者」として経済産業省から認定を受けています。
ABtCの設立と活動は、経済産業省が推進する「ウラノス・エコシステム」の一環として位置づけられています。ウラノス・エコシステムは、企業や業界、国境を越えたデータ共有とシステム連携を促進し、社会課題の解決とイノベーションの創出を目指す取り組みです。ABtCは、このエコシステムの下で、自動車・蓄電池業界のデータ連携基盤を構築し、特に欧州電池規則への対応として、蓄電池のライフサイクル全体におけるCO2排出量の開示義務に対応するためのサービスを提供しています。
今後、ABtCは蓄電池のCFPデータ連携にとどまらず、人権保護に関するデューデリジェンスやライフサイクルアセスメント(LCA)に基づく環境評価など、データ連携の範囲を拡大していく方針です。
公式HP: https://abtc.or.jp/
当社認証について: https://abtc.or.jp/news/c8fO383c
参考: ウラノス・エコシステムに準拠 | booost technologiesプレスリリース
■ 認証取得の背景
近年、企業には環境への配慮のみならず、社会全体の持続可能性に貢献することが求められています。特に、製品のライフサイクル全体における環境負荷を把握し、透明性を確保することの重要性が増しています。このような状況下で、ABtCは、経済産業省が推進する「ウラノス・エコシステム」に準拠したデータ連携基盤を構築し、自動車・蓄電池業界におけるデータ共有とシステム連携を促進することで、環境規制への対応と社会課題の解決を目指しています。
なお、日本では2027年3月期から、時価総額3兆円以上のプライム上場企業を皮切りに、サステナビリティ情報開示の義務化が始まります。当社は「サステナビリティ2026問題」を提唱し、「booost Sustainability Cloud」の提供を通じて企業の本質的なSX実現のため、制度開示に向けた業務へのデータ活用に留まらず、財務情報に加えサステナビリティ情報を戦略的に経営に利活用する取り組みを支援しています。また、当社は欧州電池規則対応など、自動車業界を始めとした業種横断的なシステム連携を強化してまいりました。
そしてこの度、ABtCの認証プログラムである「アプリケーション認証」を取得することで、「booost Sustainability Cloud」がABtCのデータ連携基盤と安全に接続できることを証明し、ユーザーに対してより信頼性の高いサービスを提供できるようになりました。今回の認証取得は、当社が提供するソリューションが高い品質基準を満たしていることを示すものであり、国際的なサステナビリティの動向に対応するものです。
■ コメント

一般社団法人 自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センター(ABtC)代表理事 藤原輝嘉 氏
この度boost technologies様のサービスが、当法人のデータ連携基盤と接続するアプリケーション認証を取得し、自動車・蓄電池業界が進める社会課題・業界課題解決の取り組みに新しく加わっていただいたことを大変喜ばしく思います。社会の持続可能性に関する課題は、様々なステークホルダーが手を取り合って進める必要がある中、確かな技術力を持ち、グローバルで活躍するboost technologies様の認証取得は、今後の取り組みを前進させる大きな力になると期待しています。

booost technologies株式会社 取締役 CTO 高塚 智敬
今回の認証は、当社の技術力とサステナビリティへの貢献を示すものです。booost Sustainability Cloud は、複雑なサプライチェーンのデータ管理を効率化し、透明性を向上。企業の持続可能な事業活動を支援します。特に、欧州電池規則への対応は喫緊の課題であり、認証取得がその解決に貢献できると確信しています。開発チームの努力を称賛するとともに、今後もより高度な技術開発に挑戦し、お客様に最高のサービスを提供してまいります。
■「booost Sustainability Cloud」について

サービスサイト
サステナビリティERP(※1)「booost Sustainability Cloud」は、自社およびサプライヤーのサステナビリティ情報を管理する“統合型SXプラットフォーム”です。ISSB、CSRD、SSBJ等のサステナビリティ情報開示基準に準拠した環境、社会、ガバナンス等の1,200以上のデータポイントに対応したサステナビリティ関連情報の収集、集計を自動化し、リアルタイムでのモニタリングを可能にします。
グローバルに対応したデータガバナンス機能を搭載しており、グループ連結やサプライチェーンを含む組織において多階層の承認フローの実装が可能であるほか、第三者保証等にも対応すべく設計したプラットフォームであり、法人外部への講演実施についての許可を申請します。関連情報の開示に向けて発生する各業務を効率化・最適化する機能をフェーズ毎に包括的に提供しています。提供開始以降、85ヶ国以上、大企業を中心に192,000拠点以上(2025年2月時点)に導入されています。
<booost PCF機能について>

会社単位のみならず製品毎のライフサイクルにおける製品カーボンフットプリント(PCF)を精緻に算定します。排出量のボトルネックを可視化すると共に、PCF改善のための高度な分析も行います。
主な機能(一部)
- PDS(プライマリーデータシェア)の管理やサプライヤーのプライマリーデータを活用した算定
- Tier1-4...等サプライヤー別に算定メソッドを管理する機能
- IDEA、ecoinvent、IEA など、グローバルなデータベースに対応
- BOM/BOP構造の取り込み、素材・部品・製造プロセス別の算定
- 製造プロセスごとの情報を基に作成した工程ごとのCO2排出量による算定製品・サプライヤー・販売先ごと、輸送ルート別の生産予測や製品PCF比較・感度・ホットスポット分析
- 生産フォーキャスト(予測)機能
- ウラノス・エコシステム、PACT等のネットワークAPIを活用したPCFデータ連携
- ISOレポート等の各種レポーティング対応
詳細は「booost PCF」機能ページをご覧ください:https://booost-tech.com/pcf
■ サステナビリティ2026問題の解決を目指す「日本をSX先進国へ」プロジェクト

「サステナビリティ2026問題」とは、サステナビリティ情報の開示義務化にあたって、多くの企業で着手が遅れており、その危機感も不足しているため、このままでは企業価値の低下につながってしまう懸念がある差し迫った状況であることです。
現在企業を取り巻く「サステナビリティ2026問題」を乗り越え、日本企業のSX推進や企業価値向上を通じたグローバルでのプレゼンス向上を目指すため当社は、2024年11月に「日本をサステナビリティ・トランスフォーメーション先進国へ」プロジェクトを立ち上げ、その解決を図るアクションに取り組んでいます。詳細は「日本をサステナビリティ・トランスフォーメーション先進国へ」プロジェクトサイトをご覧ください。
プロジェクトサイト(賛同企業募集中):https://booost-tech.com/2026sx
■ booost technologies株式会社について
当社は、国際開示基準に準拠し、環境、社会、ガバナンス等の1,200以上のデータポイントに対応したサステナビリティ情報の収集、集計の自動化及び、リアルタイムでのモニタリングを可能とする統合型SXプラットフォーム、サステナビリティERP(※1)「booost Sustainability Cloud」の開発提供を行っています。「booost Sustainability Cloud」は、グローバルに対応したデータガバナンス機能を搭載しており、グループやサプライチェーンを含む組織において多階層の承認フローの実装が可能であるほか、第三者保証等にも対応すべく設計したプラットフォームであり、サステナビリティ情報の開示に向けて発生する各業務を効率化・最適化する機能をフェーズ毎に包括的に提供しています。提供開始以降、大企業を中心に、85ヶ国以上、約2,000社192,000拠点以上(2025年2月時点)に導入されています。また、サステナビリティコンサルティング事業も展開しており、SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)領域において、企業のプロジェクト推進に伴走し企業価値向上に貢献しています。
<会社概要>
会社名: booost technologies株式会社
所在地: 東京都品川区大崎一丁目6 番4 号新大崎勧業ビルディング10階
設 立: 2015年4月15日
代表者: 代表取締役 青井 宏憲
資本金: 18億円(資本準備金含む)/2025年2月時点
事業内容: ・「booost Sustainability Cloud」の開発運営
・サステナビリティコンサルティングサービスの提供
コーポレートサイト:https://booost-tech.com/
booost及びBOOOSTは、booost technologies株式会社の登録商標です。
(※1)サステナビリティERP「booost Sustainability Cloud」は、自社及びサプライヤーのサステナビリティ情報を管理する“統合型SXプラットフォーム”です。国際開示基準に準拠した環境、社会、ガバナンス等の1,200以上のデータポイントに対応したサステナビリティ関連情報の収集、集計を自動化し、リアルタイムでのモニタリングを可能にします。グローバルに対応したデータガバナンス機能を搭載しており、グループやサプライチェーンを含む組織において多階層の承認フローの実装が可能であるほか、第三者保証等にも対応すべく設計したプラットフォームであり、サステナビリティ関連情報の開示に向けて発生する各業務を効率化・最適化する機能をフェーズ毎に包括的に提供しています。提供開始以降、85ヶ国以上、大企業を中心に約2,000社(192,000拠点以上。2025年2月時点)に導入されています。
(※2)サステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)とは
社会のサステナビリティと企業のサステナビリティを「同期化」させていくこと、及びそのために必要な経営・事業変革(トランスフォーメーション)を指す。「同期化」とは、社会の持続可能性に資する長期的な価値提供を行うことを通じて、社会の持続可能性の向上を図るとともに、自社の長期的かつ持続的に成長原資を生み出す力(稼ぐ力)の向上と更なる価値創出へとつなげていくことを意味している。(出典:伊藤レポート3.0)