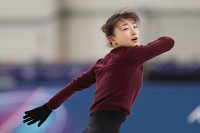下北沢の「農民カフェ」
異彩のオーナーが語る、下北沢と自分、下北沢の未来
食の大切さに気付いたら、こうなった
 ―ミュージシャンであり、飲食店オーナーあり、農業を行う一面もあり…いろいろな顔をお持ちですね。
―ミュージシャンであり、飲食店オーナーあり、農業を行う一面もあり…いろいろな顔をお持ちですね。
和気 いろんなことをやっていると思われがちですが本当は一つなんですよ。音楽をやっていることや少年院で歌っていること、飲食店を経営していること、旅をしていること、それからもちろん農業。これらを集約したのが「農民カフェ」です。
―農業に力を入れる理由を教えてください。
和気 農業は一つの表現だし、食べるということは人間の原点中の原点だと思います。生き物であれば食べていかなくてはいけない。動物は基本的に自分で食べ物を作ることができないけれど、人間は食べ物を作れるわけじゃないですか。それなら作ろうと。戦後、日本が復興していく中で、食べ物の大切さを忘れかけている部分があると思います。「金を出せば買えるもの」と。食べ物を軽く扱っているツケが、いろんな面で出てきていることに危機感を感じている、ということもありました。
―店を通して、どんなことを伝えたいと思っていますか?
和気 基本的には飲食店ですが、ギャラリーがあったり、野菜を売っていたり、ときにはゲストを泊めることもあります。食べることを原点として、いろいろなことを考えることができる場所にしたかった。具体的には、新しい農業のポジションを提案したいと思っています。わたしは国任せではなく、個人が農業を考えるべきだと思う。店で、畑で採れた野菜を使った料理を食べたり、畑で実際に農業を体験してみたりすることで、農業に参加してほしいと思います。以前から考えてきたことですが、ここ2、3年でその思いが具体化しました。
―11年前からバイクで全国の少年院を回っているそうですが、この経験も関係が?
和気 そうですね。少年院には恵まれない境遇の子も多いですが、やっぱりそういう子はちゃんとしたものを食べて育っていない。食事を作ってもらったことがない子もいる。赤ん坊はおなかがすくと泣いて、おっぱいをあげれば泣きやむ。親子のコミュニケーションの最初には「食を与えること」があります。食事は物質的にも必要だし、コミュニケーションとしても必要です。食事することで人間は成長する。きちんとしたものが食べられない子が体力も気力もなくなるのは当然ですよね。少年院での経験が、食事が大切だということを改めて考えさせてくれたというのは確かです。
音楽との出会いが、辛い少年時代を救ってくれた
 ―音楽活動のこともうかがいたいと思います。音楽との出会いはいつごろですか?
―音楽活動のこともうかがいたいと思います。音楽との出会いはいつごろですか?
和気 本能的に音楽を求めていたことは確かです。両親がいつもそばにいなくて、祖父母の家に預けられたりしていたんですが、自分がなぜそんな環境にあるのか、周囲の大人が一切説明してくれない。預けられた先が排他的な土地柄だったこともあるのかもしれないが、親から離されているというだけで「余計な子が来た」というような空気があって敵としか思えない大人ばかりでした。そんな子ども時代に、たまに聞こえてくる音楽にドキドキしたり、言葉で表現できないような思いに駆られたりするることがあった。一番印象に残っているのが、小学校になるより前に聞いた、はしだのりひことシューべルツの「風」という曲です。聞いたときに思わず涙がこみ上げてきた。この気持ちは何だろうって考えてみたら、ずっと会えなかった親に会えたときのような気持ちだった。音楽を聞いているときだけが幸せな気持ちでしたね。
―音楽に救われた、という感じですね…。
和気 それ以来、音に敏感になって、音楽が流れていると自然に耳が感知するようになった。聞いているうちに、好みが出てくる。影響を受け始める。その頃は、優しい感じの曲が好きでしたね。ロックは子どもにはわかりづらいし、歌謡曲はピンとこなかった。メロディーと訴えている言葉が胸に響くものが好きでした。
―どんなアーティストが好きでしたか?
和気 初めて買ったレコードはクイーン。買って、家でも聞きたいと思ったのは洋楽でした。言葉に煩わされずにすむからかもしれない。英語の意味がわからなかったから、言葉もサウンドとしてとらえるわけ。あまりにも言葉がズシっとくるのは、それはそれで嫌なんですよ、ストレートすぎて。もっと、曲を自分のものにしたかった。一人になったときに、音楽の中で想像していたかった。学校に行っているときも、道を歩いているときも音楽を聞きながら常に空想していたかもしれない。「もっと違う家に生まれて。この街を飛び出して、こんなところに行ってみたいな」って。
―楽器を手にしたのは?
和気 初めてギターを買ったのは中学生のとき。自分で買ったよ。ゴルフ場で打ちっ放しの玉拾いをするバイトでためたお金で自分で買いました。本当はピアノが良かったんだけど買えなかった。自分の曲を作って表現するための道具がほしかったんです。演奏ももちろん独学です。
―最初に作った曲はどんな曲ですか?
和気 フォークっぽい感じでしたね。当時は日々の不満を表現できるまでにはいってなかったと思います。でも、高校時代のキャンプファイヤーで自分の曲を歌ったら「お前すげえな」って言ってもらえて。実は中学時代荒れていたこともあったんだけど、暴力に訴えるより、音楽の方が自分の言いたいことを受け入れてもらえる、共感してもらえるっていうのが、そのころにわかった。「俺にもできるんじゃないか?バンドやりたい」って。
―転機ですね?
和気 転機はもっと前にありました。中学では荒れていたけれど、父親が刑務所に入って、その面会に行ってからガラッと変わりました。「このままじゃまずい。俺はこんな風にはなりたくない」と強く思った。だからまず必死に勉強を始めました。中3の夏でした。2学期からの4カ月で3年間分を学ぶ勢いで、ひたすら暗記して…。学校も応援してくれて高校にも入れた。自分で決めて頑張れば結果は出るという成功体験でした。
―その後、音楽の道に。
和気 最初は宇都宮駅の路上で一人でアンプを置いて…。ジャーンとならしたら、人がすごく集まってくる。それが快感でしたね。最初に組んだバンドはビジュアル系のパンクバンド。金髪にして、身体に鎖巻いて。でも、何かが違う。閉塞(へいそく)感というか。「東京でこんな格好してても驚かれない、当たり前のように受け入れてくれる」と思ったら、どんどん気持ちが東京に行き始めて。
待つのは子どもの時からいや。自分から仕掛けるのがいい
 ―それで、東京に出てきたわけですね。
―それで、東京に出てきたわけですね。
和気 渋谷・原宿あたりのストリートを拠点にしたかったんです。ライブハウスはノルマとかあるので。渋谷に近いところに住みたかったけど高くて住めなくて、探したらどんどん都内から離れて。結局、溝の口で家賃3万円の家を見つけてバスで通いました。家賃3万だけど2部屋あったから、曲作りもここでできた。
―当時はどんな生活ぶりでしたか?
和気 とにかくバイトと音楽づけ。朝6時半から昼の2時くらいまでウエーターのバイトをして、それからずっと音楽の練習。全然遊ばなかった。4年間くらいそんな生活でした。世の中はバブルで浮かれていたけれど、そんなの関係ないと思っていた。
―その頃、音楽での収入は?
和気 ストリートで、カセットテープ1本売って1,000円。それが結構売れたので、それでスタジオ代や機材代を払いました。ライブは1カ月に20本くらい。時給650円のバイトとライブの収入を合わせて、バンドの経費引いても月に15万円くらい入ってくるようになって、飯が食えるようになりました。
―当時は、どうなりたいと思っていたんですか?
和気 ライブハウスでなく、ホールでやりたいと思っていました。だから、メジャー行く前に渋谷公会堂でライブをした。周りが驚いていました。俺たちの力ならまだ無理だって言われていたから。ぴあを通さずに自分たちでチケットを売って、2千枚を完売しました。
―歌を歌うだけではなく、自分たちでライブ会場を決めてチケットを売る。和気さんのプロディーサー能力はこのころから発揮されていたんですね。
和気 待つのが嫌なんです。待たされるのが。人に指図されるのも嫌。人に使われたくない、自分で稼ぎたいとそのころから思っていましたね。子どものころから深く刻み込まれていたのかもしれません。待つのではなく、仕掛けるしかないんだって。
―どうやって会場と交渉したんですか?
和気 お金を出してくれるパートナーに、自分からプレゼンするしかない。ストリートでやっていて、これだけの集客力があると売り込む。そうやって動いているうちに、「メジャーじゃないバンドが渋谷公会堂をいっぱいにしようとしている」ってメディアやメーカーが興味を持ってくれた。ライブが終わって、アンコールはいつものライブハウスでやるって言ったら大勢の客がそのままついてきた。関係者や客に、「俺はこれがやりたかった」って見せたという達成感がありました。
―なぜ、それができるという自信があったんですが?
和気 失敗したら怖いけど、同じことをこれからずっと続けることのだるさよりはマシだった。とにかく、上にも下にもいかないような状態じゃなくて、自分のしようとすることがそのイメージ通りになることに挑戦したかった。失敗してもいいから。達成した瞬間の快感を味わいたかった。
―3年間メジャーで活躍した後、契約更新を断ったそうですね。その理由は?
和気 メジャーになると売れなきゃ売れないで、規模が縮小する。誰かに枠を持たされている感じが嫌だと思ったんです。それでバーを始めました。店を作って、そこに人を招いて、自分たちもそこに集まれるようにして、社交場を作ればいいじゃないか。かつ、その利益を自分たちに還元できればいいじゃないかって。
―それで、店を出したんですね。
和気 そう。日比谷の野音までいって、次は武道館、東京ドームまで行くって真剣に考えていました。でも、「もうこのへんでいいんじゃないの」という周りの空気を感じたし、誰かの力に頼るなら100%自活してやりたいと。そのためには、自分たちで飯食わなきゃいけない。援助金もらったりして生ぬるい生活をするくらいなら、自分たちで稼いで、自分たちで生きていこうと。それでバンドの仲間と最初に三軒茶屋にバーを作った。本当は下北沢に出したかったんだけれど、たまたま当たっちゃった。それが店を出す始まりだったんだよね。
―それまでは店を運営したことはなかったんですよね?
和気 高校のころから飲食店でバイトしたり、宇都宮にいた時は店を1軒任されたりしていたから全くの素人ではなかった。でも、店を始めたときに、食物の素材に関して急に疑問に思った。スーパー買ったものを出すのでいいのかな、と。どっからきて、誰が作っているのかわからなくていいのかなって。
―店の経営だけではなく、音楽活動も続けたんですよね。
和気 ええ。店が繁盛して、音楽のモチベーションも下がっていたんですが、そこに、日本テレビのドラマのプロデューサーから「TOKIOが歌う主題歌を作ってくれ」という話がきて。結構売れました。
―存じています(笑)。
和気 そのころ、中学時代の友だちが亡くなるという事件があったんです。それでまたいろいろ考えて、それが少年院をバイクで慰問する旅のきっかけになりました。その旅をきっかけに農家の人と出会って、さらに食べ物や音楽のこと、子どものころからの思いについて考えるようになった。「これらを一つにしなきゃいけない」と。
若者はもっと賢く、したたかになれ
 ―それで、下北沢に自然食のレストラン「チベットチベット」をオープンさせたんですね。ついに、下北沢進出ですね。
―それで、下北沢に自然食のレストラン「チベットチベット」をオープンさせたんですね。ついに、下北沢進出ですね。
和気 下北沢はいい街だと東京に来たときから思っていた。渋谷にも新宿にもアクセスしやすい。ある程度東京に住んで、渋谷や六本木に飽きた人たちが来るというイメージがあった。「住む」と「遊ぶ」が一つになった街というか、独特の文化がある。
―下北沢に3店舗も持てる。その成功のコツは?
和気 それは、ひとえに根性でしょう。飲食はやろうと思えば始められる。でも、すぐ挫折してしまう人も多い。根性がないと続けられない。
―店を出せたら終わりではない?
和気 続けないと意味がないと思うんです。だけど、今の下北沢は店を出したいと思っている人の情熱をぶっ飛ばしてしまうくらいお金がかかりますよね。初期費用だけでも。若者にチャンスを売っているようで、実は若者のエネルギーと情熱を奪い取っている街だと今は思っています。土地を持っているオーナーが若者からエネルギーを吸い取っていいのかと叫びたい。
―難しい問題です。
和気 自分だって若いときには大人からチャンスをもらったんじゃないのかと。若い人に高い家賃を払わせてチャンスを奪うなんてもってのほか。若い人にチャンスをあげるのが大人の役目でしょう。
―今、若者に一番言いたいことは?
和気 もっと賢くなれ、したたかになれ。意味のないことに、お金を持っていかれるな。拒絶すれば、マーケットは断たれて大人も考え直すかもしれない。家賃が高ければ、シェアハウスでいいじゃない。人が住まなくなったら、家賃を下げるしかなくなる。生きているわけだから何でもできる。要は、そのきっかけや可能性ですよ。農業を若者に教えることで、若い人に「自活」の精神を教えられればと思っています。今の時代の主役は若者。俺じゃないんでね(笑)。
―下北沢に望むものは?
和気 やっぱり若者にチャンスのある街であってほしい。このままだと、下北らしさがなくなってしまう。それは嫌ですね。俺にやる気と可能性を与えてくれた街というのは確かだから。
<プロフィール>
和気優(わき・ゆう)さん。1964(昭和39)年生まれ。栃木県出身。ミュージシャン、音楽プロデューサー、店舗・農業プロデューサー。20歳で上京。バンドJACK KNIFEを結成。1997年、活動休止。以来、TOKIOの「フラれて元気」「この指とまれ」をはじめ、多くのアーティストに作詞作曲のプロデュースを手がける。2000年、ダイニングバー「チベットチベット」をオープン以後、「ロータスカフェ」、2009年にオープンした一軒家のレストラン「農民カフェ」を経営。無農薬の野菜や自作米を提供している。千葉に水田を持ち、農作業も行う。また、11年前からギターを片手にバイクで全国数十カ所の少年院を回り、ライブで思いを伝える旅を続けている。その経験を元に執筆した「少年院ロックシンガー」(青志社)が発売中。http://www.you-waki.com/
(文責:佐藤智子)